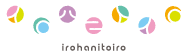vol.49-68 支援者が障害を作っている?!

支援とは“愛する”ということ(4)
前回の続きです
「愛する」ことは技術である
それはどんな技術なのか
そんなお話をさせていただいています
社会心理学者エーリッヒ・フロムは「生産的な愛」には以下の基本的要素があると言いました
〇 配慮
〇 責任
〇 尊敬(尊重)
〇 知(理解)
「配慮」と「責任」については前回説明したので、
今回は「尊敬」と「知」について説明させていただきます
〇 尊敬(尊重)
※「尊敬」と聞くと誤解しそうなので「(尊重)」と書きました。本来の尊敬とは、目上の人を敬う行為ではありません。以下の内容が本当の「尊敬」の意味になります。
尊敬とは、相手がその人らしく、成長発展していくように気遣うこと
相手も一人の独立した人間であり、自分と同じ価値ある大切な存在である、ということを認めることです
つまり、
その人がこの世で唯一無二の価値ある存在だということを知る能力のことです
その人が唯一無二の存在だからこそ、その人らしい成長発展を願い、見守り、気遣うことができる、ということですね
なんか「能力」と言われると身が引き締まる思いになりますよね
私たちがよく口にする
「あの先生を尊敬する」
「尊敬するあの人みたいになりたい」
というものは、本当の意味での尊敬ではなく権威(目上の人)への従属だったりします
未熟で問題だらけに見える人も
自分とは意見が異なる人も
年齢や立場や経験値に関係なく、唯一無二の価値ある存在として見るということです
この世界には何人の人間がいるかご存知ですか?
82億3,200万人なんですって!(2025年現在)
82億3,200万人は全員違っていて、
その中の一人が目の前の人!
なんか凄いことですよね!
だってこの人と同じ人はこの世界に一人もいないんですよ!
82億分の1の私と82億分の1のあなたが出逢っているなんて、これだけで奇跡ですよね
(67240000000000000000分の1の出会いをしています)
なんかそんなふうに考えていくと、尊敬は「相手が唯一無二の存在だと知る能力」だという意味が分かる気がします
〇 知(理解)
相手の立場に立ってその人を見て、その人を知ることです
相手を知ることによって自分自身を知るという意味も含んでいます
他者と関係性を持つことで初めて自分自身が見えてくるのです(他者と自分は違うということ)
つまり、どういうことかというと
「もし自分がその人なら」と相手の立場に立って想像する力のことです
もしも、自分が相手と同じ心と同じ体を持っていたら?と想像すること
相手の目で見て、相手の耳で聞いて、相手の体で感じることです
私たちは皆違う個体なので、完全に相手の立場に立つことはできません
しかし、想像する努力は出来ます
相手と同じ感覚になれることが愛なのではなく、
同じ感覚を想像し、その人をより理解しようとする
その行為が「愛」なのです
つまり結局のところ「対話」ですね
「愛」は対話
「対話」は愛
そんな風に僕は繋げてしまいます
だからあなたの声を聞かせて欲しい
あなただどうしたい?
何を考えている?
どんなことを感じている?
関わり自体が対話となっている
「支援しない支援」
とは
「対話的支援」
と言い換えられるのかもしれません
※もちろん「言葉(声)」に出来ない人もいらっしゃいます。対話とは言葉(声)の表現だけということではありません。表情も行為も対話だし、文字としても対話もあります。
ちょっと無理くりすぎましたかね?
自分でも少し急ぎ過ぎた感覚があります(笑)
でもこのシリーズもいい加減終わりにしたいと思っているので、あと2回で最後にしたいと考えています
つまり「支援者が障害を作っている」ということはどういうことか
それに気付いた私たちはどんな支援をしているのか
そうすることで何を目指しているのか
それをまとめて終わりにしたいと考えています
最後に「愛する」ことについて重要なことをお伝えさせていただきます
社会心理学者 エーリッヒ・フロムは、「愛する」ことをこのように説明しました
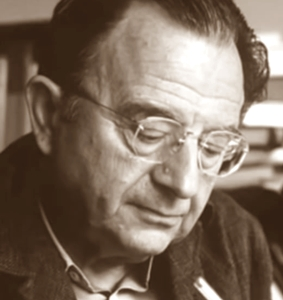
「愛は能動的な活動であり、受動的な感情ではない。
その中に『落ちる』ものではなく、『自ら踏み込む』ものである。
愛の能動的な性格を分かりやすい言い方で表現すれば、
愛は何よりも与えることであり、もらうことではない、
ということができよう」
「与えるということは、
相手を“与える者にする”ということであり、
互いに相手の中に芽生えたものから得る喜びを分かち合うのである。
与えるという行為の中で何かが生まれ、
与えた者も与えられた者も、互いの為に生命に感謝するのだ」
ここ意味分かりにくいですよね?
「愛する」ことを
相手を甘やかすことだったり
相手の言うことに従うことだったり
相手の思いどおりにさせることなのではないか
と勘違いしないでいただきたいんです
実はその行為の裏には、こちら(親や教師や支援者)の都合、
つまり私が
傷つきたくない(相手の困っている姿を見たくない)
面倒なことを背負いたくない
責任を持ちたくない
そんな自己中心的な考えが潜んでいるのかもしれません💦
一見すると優しくて良く見える支援者
実ははその正体は、無責任で自己中心的な人なのかもしれません
(昔の僕がまさにその通りの人間でした💦)
支援者が自分を守り、自分の自尊心や有能感を満たすために、障害者を利用している、
あるいは作り出している
こんな恐ろしいことが起こっているかもしれないということをこのシリーズでは訴えかけてきました
エーリッヒ・フロムさんが言っているように“与える者にする”ということが大切だと思っています
「支援しない支援」が
愛に基づいた支援であり
それは「対話的」な支援
そしてそれは、メンバー(利用者)の方々を“与えられる者(弱者)”ではなく
自分たちが主体的に行動し他者に貢献していく
そんな“与える者”になっていくということだと考えています
すみません💦
めっちゃ長くなってしまいました💦
まだまだこの内容で書けそうなのですが、あと2回でまとめて「vol.49」を終えたいと思います
最後までお読みいただきありがとうございました
イロハニトイロ所長
金村栄治