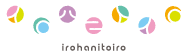vol.49-60 支援者が障害を作っている?!

支援しないという支援(5)
前回の続きです
イロハに来てくださっている実習生(学生)の質問を使わせていただいて、
「支援しないという支援」についての具体例をお伝えできればと考えています
【質問1】
BGMの音楽はどのようにして決めているのですか?
学生さんの意識としては、
きっと支援者が意図を持ってBGMを決めているのだろう
利用者さんにとって良い効果になるように考えられているに違いない
それを知りたい
そんな思いがあるようです
これがよくある支援者の感覚ですよね
「作業に集中させたいから、歌詞のない音楽を流そう」
とか
「利用者同士のトラブルになるから流す曲はあらかじめ決まったものにしておこう」
とか
「音楽が不快な人もいるから最初から仕事中は流さないようにしよう」
とかとか
相手を良くしようとしてますよね
支援者としての役割を果たそうとしていますよね
でも本当は
トラブルになって面倒なこと起こしたくない支援者の管理意識によるものからかもしれません💦
表面上は「利用者のため」と言いながら💦
もちろん支援者はそんなこと気付きもしません💦
それではイロハではどうしているのか
「支援しないという支援」とは、
BGMについて何も操作しないんです
そうすると何が起こると思いますか?
そうです!
トラブルが起こるんです!
「音が大きくて気になる!」
とか
「クラシック曲は嫌い!」
とか
「この曲は昔のことを思い出して苦しい」
とかとか
つまり“困る”人が出てくるということです
「困る」という不快があると、人はどうするでしょうか?
イロハに来た多くの人が最初はこのようにします
①我慢する
この精神が染みついているんですよね
私が我慢すれば上手くいく
そうやって生きざるを得なかった方が多いですから💦
でもそれだとずっとこの私は苦しいままなんです
じゃあ、どうすればいいかというと
②相手と話をする
「音量を少し下げて欲しい」
とか
「この曲はちょっとしんどいので変えてもいいですか?」
とかとか
でもですね、この②が出来ないから苦しんでいるわけですよね?
どうして②ができないのか
それは
・勇気がない
・どう伝えていいか分からない
・上手くいかないかもしれなくて不安
・仲が悪くなりたくない
とかとかあるわけです
そうすると支援者は
②の練習をすることを正しいことだと伝えます
そして
頑張ってできるようになることを応援します
イロハは、それともちょっと違うんです💦
だってですね、
解決策は①か②しかないんでしょうか?
そんなことありませんよね
他には
・耳栓(イヤホン)をする
・部屋から出ていく
・不快な態度を見せる
・無言で音を消す
・同じ思いをしている人がいないか周囲の人に聞いてみる
・スタッフに相談する
などなど、もう無数に存在するんです
こんなふうに対処のコマンドがたくさんあることが生きやすさにつながるんです
自分に合った方法を使えばいいし、
その場面に合った方法を使えればいいんです
それを「②相手と話をする」だけに限定しないのがイロハです
でも面白いのが大抵は皆さん②が一番効果的だと分かって、
上手く相手と話をして折り合いをつける方法を身につけていきます
話が長くなってすみません💦
つまり「支援しないという支援」とは、
まず「困ること」がスタート
そして「困る」をどうにかしようとする
その方法は無数にある
自分の生き方に合ったものを身につけていく
その時に相談出来たり力を借りられるのがスタッフ(支援者)や他の利用者さん達なんです
これは「支援しようとしない姿勢」
から生まれるんです
「支援しよう」と思った途端に世界を二分し、
強者と弱者が生まれ正しさと誤りという価値観の偏りが生まれる
それをしないからこそ、
利用者さんが自らの意思で行動し始め、支援者はそのお手伝いをする
そんなお話ですが、まだまだ分かりづらいですよね
次回も「支援しないという支援」の具体例を学生の質問を取り上げてご説明させていただければと思います
最後までお読みいただきありがとうございました
イロハニトイロ所長
金村栄治