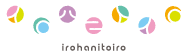vol.49-㊱ 支援者が障害を作っている!?

自立させようとして自立を妨げている支援者(3)
どうして支援者は、患者さん(利用者さん)を自立させようとして自立を妨げているのでしょうか?
前回お話したように、支援者自身が責任逃れをしたいからです
責任を回避するためには、自分に従わせて支配下に置く方がいいからです
もちろん支援者はそんなこと思っていません
むしろ責任を持って仕事をしていると思い込んでいます
(僕自身がずっとそうでしたから、こんなこと信じられるはずがありません)
支援の現場では「ラポールの形成」という言葉がよく使われます
「ラポール」とは担当患者さんと信頼できる関係を築くことです
そしてその「ラポールの形成」が、
信頼感を高めて支援者の指示に従ってくれるようになること、のように勘違いされている気がします
本来逆ですよね
本当の信頼関係って逆なはずです
むしろ信頼関係ができているから、怒りも出せるし反抗もできる、自分の意見を主張できる
それこそが本当の信頼関係だと僕は思うんです
だって、支援のゴールは「自立」なんですよね
「自立」するって、
自分で判断し、行動できるようになることです
支援者の支配下に置く行為は、どんどん自立から遠ざけています
何度も言っていますが、誰もが「愚行権(ぐこうけん)」という愚かな行いをする権利を持っています
間違う権利です
失敗する権利です
この行為を通じて、学び成長していくわけです
子育てのよくある場面で考えてみると
忘れ物の多い子どもに対して、忘れ物をしないようにお母さんが
チェック表を作ったり、声掛けしたり、
困らないように忘れ物を届けたりする
こういうことありますよね
お母さんは、忘れ物をしないように躾けているつもりです
子どもの将来の自立に向けて
でもこれが忘れ物をする人間を作っていく
つまり「自立」を妨げているわけです
忘れ物をして「困る」「恥をかく」という経験が本来大切です
だから自分で「忘れ物をしないようになりたい」と望む
その時に子供が相談できる相手として親がいる
そしてどうするのかを一緒に考える
つまり出発点は子ども(本人)できゃならない
子どもが自分の力で忘れ物をなくせるようになる
そのために親を使う
これが自立につながっていくわけですよね
支援も同じだと思うんです
って語りたくなったのですが、長くなってきたので次回にさせていただきます。
このお話、まだまだ続きます。
どうぞお付き合いください。
イロハニトイロ所長
金村栄治